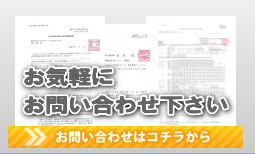行政書士 おおこうち事務所
フリーダイヤルも お気軽にご利用ください メールでのお問い合わせ ご相談はこちらから  24時間受付 このページを お気に入りに追加する! 相互リンク集1 相互リンク集2 サイトマップ 行政書士登録のご確認は こちらから  日本行政書士会連合会 会員・法人検索  行政書士おおこうち事務所 〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201号 TEL:045-325-7550 FAX:045-325-7551 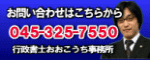 お問い合わせはお気軽に
 主な業務対応地域 横浜市、川崎市を中心 として神奈川県全域と 東京23区に対応 その他 業務に応じて上記以外の 地域においても対応させて いただいております。 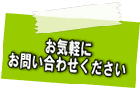 身近な相談相手として 行政書士をご活用ください。 |
建築士事務所登録 (一級建築士・二級建築士・木造建築士) 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)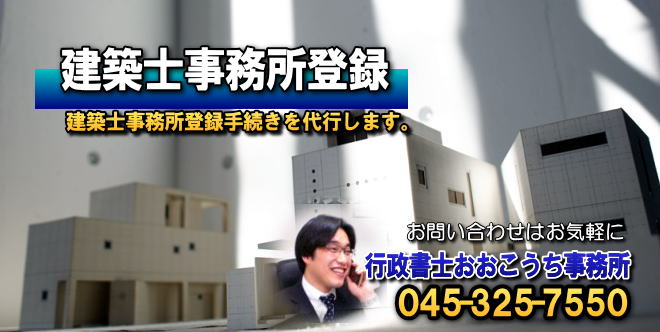
建築士事務所登録 横浜建築士事務所登録 建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の設計、建築物の設計工事監理、 建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定、建築物の建築に関する 法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理などの業務を行う場合は、建築士事務所を定めて、その建築士 事務所について、都道府県知事の登録を受けなければなりません。 さらに、建築士事務所は扱える建物の規模・構造などに応じて 「1級建築士事務所」 「2級建築士事務所」 「木造建築士事務所」 に分けられます。 当事務所では新規登録申請から登録後の各種変更手続きまで幅広くサポートさせていただいております。 建築士事務所登録が必要となる業務(建築士法第23条)
業務も行う場合は、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録も必要となります。 営業所等に関して建築士事務所の登録が必要となります。 建築士事務所の登録要件(登録の基準) 一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所は専任の二級建築士が管理し、 木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理することになります。 これらの管理者が管理建築士となり、それぞれの建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、 事務所開設者に対して技術的観点から、業務が円滑かつ適正に行われるよう、必要な意見を述べる職務を 担うことになります。 管理建築士は、原則として、事務所に常勤し管理建築士としての職務を行うことになります。 従って、事業主と雇用契約等により継続的な雇用関係を有し、事務所の休業日等を除いて通常の勤務時間中は その事務所に勤務していなければなりません 非常勤の役職員や派遣社員、法人の監査役、他の法令等で専任性が求められる職務に就いている者、 管理建築士の住所と事務所所在地のが遠距離で、常識的に見て通勤が不可能な距離にある場合などは、 原則的には管理建築士になることはできません。 ただし、都道府県での取り扱いの違いにより、他法令により専任性が求められる場合でも兼務が認められる 場合もあります。
建築士事務所の管理建築士になるためには、建築士として3年以上設計その他国土交通省令で定める業務に 従事した後、管理建築士講習の課程を修了することが必要となります。 新規で建築士事務所を登録する場合には、必ず管理建築士が必要となり、管理建築士講習の修了証の写しを 提出するする必要があります。 建築士事務所の登録をするためには、設計等の業務を行う事務所を設ける必要があります。 事務所に関しての広さや設備等の条件は特に定められていませんが、常識的に建築士としての業務が出来る程度の 広さや設備を有している必要があります。 登録申請者が以下に該当する場合は登録が拒否されることがあります。
建築士事務所 登録後の義務 建築士事務所の開設者には、建築士法の規定により次の義務が課せられることになります。 1.標識の掲示(建築士法第24条の5) 建築士事務所開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める 標識(建築士事務所の名称、登録番号、開設者、管理建築士名、登録の有効期間の標示)を掲げなければ なりません。 2.帳簿の備付け及び図書の保存(建築士法第24条の4) 建築士事務所開設者は、その業務に関する事項で、毎事業年度毎の契約の相手方、契約の種類、その概要、 報酬の額等を記載した帳簿を事業年度末日の翌日から15年間保存しなくてはなりません。 また、事務所に属する建築士がその建築士事務所の業務として作成した設計図書等に関しても、作成から 15年間保存しなくてはなりません。 3.書類の閲覧(建築士法第24条の6) 建築士事務所開設者は、国土交通省令で定めるところにより、以下に掲げる書類を事務所に3年間備え置き、 設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧をさせなければならない。 1..当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類 2..当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類 3..設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結 その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類 4..その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの 4.重要事項の説明等(建築士法第24条の7) 建築士事務所開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(設計受託契約又は工事 監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、建築主に対し、その事務所の管理建築士その他の 当該建築士事務所に属する建築士に、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する 重要事項について書面を交付して説明をさせなければなりません。 5.書面の交付(建築士法第24条の8) 建築士事務所開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で 定めるところにより、設計又は工事監理の種類及びその内容、設計又は工事監理の実施の期間及び方法、 報酬の額及び支払いの時期、契約の解除に関する事項等を記載した書面を委託者に交付しなければなりません。 6.設計等の業務に関する報告書の提出(建築士法第23条の6) 建築士事務所開設者は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、当該建築士事務所の業務の実績の概要や所属する 建築士の当該事業年度における業務の実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、提出しなければ なりません。 その他、「再委託禁止」や「立入検査の協力義務」など、建築士事務所開設者には多くの義務が課せられます。 建築士事務所の更新登録申請 建築士事務所登録の有効期間は、登録の日から5年間です。有効期間の満了後も引き続き業務を行う場合は、 有効期間の3ヶ月前から30日前までに更新申請の手続を行う必要があります。 有効期間を過ぎると登録は抹消されますので、更新時期を忘れないように管理と十分な注意が必要です。 建築士事務所の登録事項変更届 建築士事務所登録後、以下の登録内容に関して変更が生じた場合、2週間以内に都道府県知事に 届け出なければなりません。(神奈川県の場合、窓口は社団法人神奈川県建築士事務所協会になります)
建築士事務所登録手続はお任せください 登録申請をはじめとした役所への手続きや折衝は専門家に任せて、経営者の方は本業にご自身の力を 注いでください。 多少の費用負担はあっても、経営者の方にはメリットの方が大きいことでしょう。 建築士事務所の登録に関する手続きは当事務所にお任せください。 ご相談は無料でお受けしております。 まずはお気軽にお問い合わせください。 建築士事務所登録申請手続代行
※ 登録申請手数料に関しては別途申し受け致します。(申請手数料は神奈川県の場合です) 一級建築士事務所¥15,000- 二級・木造建築士事務所¥10,000- ※ 登記事項証明書取得費用等の実費費用に関しては別途申し受け致します。
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 ホーム 事務所案内 | 取扱業務&料金 | 業務の流れ | 行政書士とは | お問合せ(メール相談) 個人情報保護方針 | 特定商取引法に基づく表示 | リンク集 | 相互リンク集1 |相互リンク集2 | サイトマップ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||